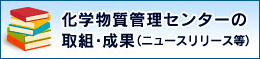| 名称 |
第11回レスポンシブルケア 山口西地区地域対話 |
| 実施日時 |
平成29年11月10日(金) 13:30~17:45 |
| 目的 |
化学品を扱う企業が開発から最終消費に至る全ての過程において自主的に環境、健康安全を確保しその成果を公表し、社会との対話・コミュニケーションを行う自主活動 |
| 場所 |
ANAクラウンプラザホテル宇部 〒755-8588 山口県宇部市相生町81 |
| 実施主体 |
日本化学工業協会RC委員会山口西地区(日産化学工業、UMGABS、日本化薬、下関三井化学、宇部興産、セントラル硝子) |
| 規模・参加者構成 |
自治会72名
行政・学校関係47名
近隣地区企業(日化協含む)20名
山口西地区会員企業29名
高校生等23名
総計137名 |
| 実施内容 |
- ①開会挨拶(セントラル硝子宇部工場)
- ②来賓挨拶(宇部市長)
- ③DVD上映「暮らしのそばに化学のホント?レスポンシブルケアってなあに?」
- ④基調講演「暮らしに役立つ高分子ー身近なものから、最先端までー」山口大学 堤宏守教授
「臭気問題への取り組みー測定・評価・対策の基礎と最近の展開ー」 山口大学 樋口隆哉准教授
- ⑤アンケート結果報告 セントラル硝子
- ⑥レスポンシブルケアへの取組状況(宇部興産、UMG ABS、日産化学)
- ⑦意見交換会 事前アンケートの意見、要望に対する回答及び質疑応答
- ⑧閉会挨拶 下関三井化学
|
| 説明内容(予稿集以外で特筆すべき事項) |
- ④予稿集に沿って説明。
- ⑤住民が関心を持っていること(臭気20%、水質汚染16%、火災・化学物質汚染13%)。環境・安全で日頃から期待されていること(臭気、騒音、大気、水質等34%、工場の火災・爆発の防止28%)
- ⑥敷地境界で臭気濃度測定(宇部興産)、アクリルニトリル大気排出量を7%、スチレンの大気排出量を3%削減、異常事態対処訓練を実施(UMG ABS)、火災や漏洩等の未然防止に努め、対応訓練を実施。近隣住民への連絡のため広報車。(日産化学)
|
| 参加者からの質疑 |
ファシリーテーションは山口大学関根教授によって行われた。
- 壊れやすい高分子の開発をしてほしい。数千の分子量をもって壊れやすいような高分子。
- 宇部の町でにおいを感じるとき、吸ってても大丈夫なのか?
- 公害に対する企業と行政に係る姿勢について、企業への立ち入り検査について聞きたい。
- 日産化学は南海トラフ対応を考えているが、南海トラフよりも周防灘地震のほうが津波の被害が大きいと想定されている。津波到達時間は25~26分、震度6強、津波波高は3.5m。建物高さなど周防灘地震に対応しているのか?
- 見学している途中で危険物をこんなに使っているんだということを感じた。対話が今回の情報公開に繋がっていると考える。持ち帰って検討するとしているが今後の情報公開を各社どのような形を考えているのか?
- 危険物質としてスチレンモノマは危険だと思う。A社が入っていない理由は?
- A社は参加していないが、危険性があると考えて質問した。今後、会員数を増やすことはどうか?
- VOCの臭気抑制燃焼装置について、有機の揮発性物質をたくさん使っているので良い取り組みと思うが、県の基準値市の協定をクリアしているのか?他社さんの導入は難しいと思うが、導入状況を聞きたい。
- データ公表の仕方について。においの数値のデータ。6月のデータを公表しているが、平均値、最大値はどうなのか?他の物質はどうなのかと考えてしまう。
- 何通りか化学物質を合成する方法はある。廃棄物や効率性、危険なものを使わないなど安全性を優先するのか、幾通りの方法がある。モノづくりに生かす方法も研究されている。
- 企業内のプロセス安全について。
|
| 特徴的な取組 |
周防灘地震で想定される津波対策、情報公開のあり方など、適切なファシリテーションのもと、建設的な意見交換が行われた好例である。 |
| 開催案内の方法 |
周辺自治会、行政、学校等に呼びかけ。継続して行われている。 |
| 当日参加者に準備したもの |
- 式次第
- 予稿集
- CSR報告書
- アンケート
- 封筒
- 筆記用具
- お茶
|
| リスクコミュニケーション活動の公表状況 |
レスポンシブルケアニュース 2018年春季号に掲載。 |